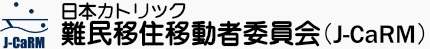(カトリック新聞2020年10月25日号掲載)
日本にはさまざまな事情で暮らす、いわゆる「非正規滞在の外国人」が大勢いる。しかし、日本政府は彼らの個別の事情を考慮せず、既に「出入国管理及び難民認定法」(入管法)上の退去強制令書が出ていることを根拠に、法務省・出入国在留管理庁(以下・入管)の収容施設に無期限で長期収容したり、強制送還を行ったりしている。「非正規滞在の外国人」への人権侵害を考える連載第18回は、日本と世界の難民認定基準の違いについて。
日本の難民認定率は、先進諸国の中でも、また難民条約加盟国の中でも極端に低い。昨年、日本で難民認定申請をした人の数は1万375人。そのうち難民認定された人はたったの44人で、難民認定率は約0・4%だ。日本が「難民鎖国」といわれるゆえんである。
「条約難民」さえ保護しない
この難民認定率の低さの原因になっているのが、難民認定に関する「日本の独自ルール」の存在だ。難民支援に尽力する高橋済弁護士は、今年9月29日のオンライン緊急記者勉強会でこの「日本ルール」についてこう話した。
「『日本ルール』は、主に四つありますが、一番の問題は『個別把握説』といわれる〝独自ルール〟です。本来、難民条約加盟国であれば、難民条約で定義された『難民』(以下『条約難民』)を『難民』として認めるはずなのに、日本では『条約難民』でさえ『難民』として認定しません。それは難民一人一人を疑ってかかる〝日本独自のルール〟があるからです」
難民条約で定義される「難民」とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、また政治的意見を理由に、迫害を受けている者、あるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃げた者」を指す。これらを総称して「条約難民」と呼んでいる。
世界には、イスラームからキリスト教に改宗したら死刑になってしまう「信教の自由がない国」がある。Aさんという人が、そうした国から逃れてきた場合、難民条約による「国際基準」では、たとえAさん自身に、迫害を受けた経験がなくても、周囲に同じ条件で迫害を受けている者がいれば、Aさんも「難民」として認められる。「迫害を受けるという十分に理由のある恐怖」を抱えていると、合理的に判断されるからだ。
一方「日本ルール」では、Aさん個人に、逮捕状や殺害予告状があるなど、Aさん自身が「特別に」迫害の対象になっていることを自ら立証しない限り、「難民」としては認めてもらえない。
また世界には、政府批判を行ったら監禁・暴行を受けるといった「言論の自由がない国」も多く存在する。この状況を「日本ルール」に照らし合わせて、高橋弁護士は次のように説明した。
「言論の自由がない国で、メディア関係者がほとんど殺されるという状況であれば、その国から逃げてきたメディア関係者は全員、難民条約では『国際基準』によって『難民』として認められます。ところが、日本の場合は、記者個人が、政府から『殊更に』注視(ターゲットと)されていなければならず、その証拠として命を狙われた物的証拠がない限り、いくらその国から逃げてきたとしても『難民』として保護はしません。この『日本ルール』こそが、日本を『難民鎖国』にしている原因になっています」
しかも、「日本ルール」の場合は、自分が迫害を受けた事実を、自分自身で立証しなければならない。しかし、自分が政府関係者から銃を向けられているその瞬間の出来事を、自分で撮影して証拠を残すことは不可能だ。それでも、必死の思いで物的証拠を出しても、日本では難民認定されないという〝不可思議な現象〟が多発している。
つまり、日本は難民条約に加入していながら、同条約の「国際基準」を完全に無視し、「条約難民」でさえも難民認定しない状況を続けているのだ。これにより、難民認定申請者が全く同じ条件下で母国を脱出した場合であっても、カナダや米国では難民認定され、日本では難民認定されないという現象が起きてしまうのだ。
「準難民」制度では改善されない
日本政府は、早ければ今秋の臨時国会で入管法改定案を上程する予定だが、その改定案に盛り込まれるといわれているものの一つが、「準難民」制度の新設だ。
9月22日付読売新聞の1面トップ記事で、入管法改定案の〝中身〟が一部公表された。その一つとして「準難民」制度の新設をアピールし、難民認定申請者らにも〝明るい未来〟が開けるような印象を与えた。
記事によれば、「準難民」制度とは、難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できない「戦争難避民」らを、「人道的配慮(保護)」が必要な人として「準難民」に認定し、在留資格を与えて保護するというものだ。
この「準難民」という言葉は、今回初めて出てきた「造語」だが、実は、その対象は現在の「人道配慮」措置と同じもの。昨年、日本では難民認定申請者のうち37人が、「人道配慮」措置を受けた。これは、「条約難民」として認められないものの、さまざまな理由から母国への帰還が難しく、保護すべき対象となり、在留資格が与えられた者のことだ。しかし、この保護率も実際には約0・35%と低い割合になっている。
同記事では、「準難民」制度によって、「難民鎖国」の問題が解決できるといった印象を与えようとしているが、高橋弁護士はその根本の誤りをこう話す。
「『難民鎖国』の問題は、『戦争避難民』を保護していないことが原因ではなく、そもそも『条約難民』を保護していないことに要因があるのです。いくら『準難民』制度ができても、全く問題は解決しません。保護すべき難民を保護していく。これに尽きるのです」
外国人の人権擁護に尽力する弁護士たちは、「今回の記事にだまされないように」と注意を喚起し、「世界人権宣言」や国際法に合わせて、入管法を本来あるべき姿へと改正していく必要を強く訴えている。

茨城県牛久市にある東日本入国管理センター(通称・牛久入管)にも、多くの難民認定申請者が収容されている

牛久入管で、何度も自殺を図ったクルド人の難民認定申請者、デニズさんの姿を仲間が描いたもの。命は取り留めたが、現在も在留資格は得られず苦悩する